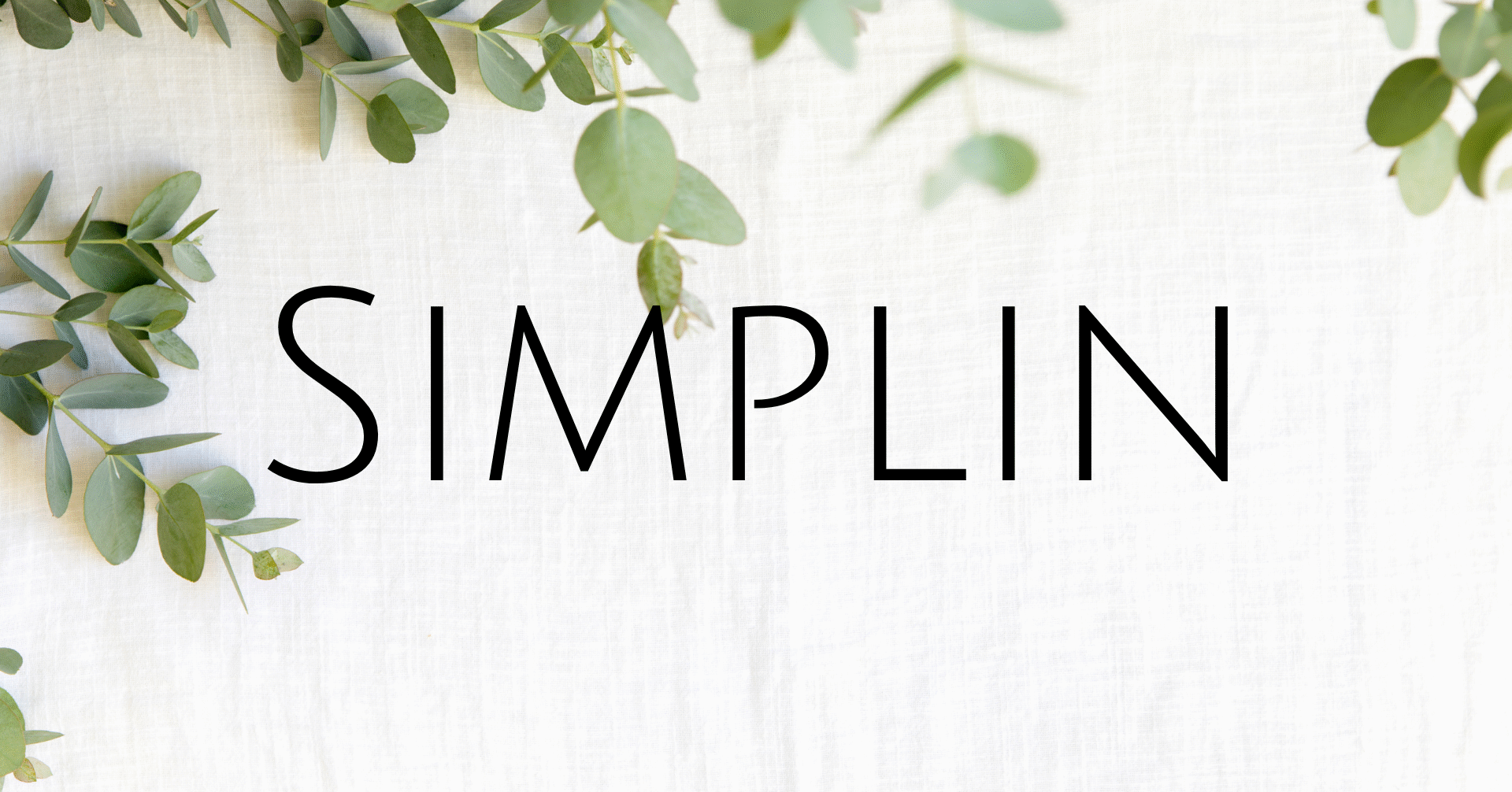8月9日はシンガポールの建国記念日。1965年にマラヤ(現在のマレーシア)から独立し、2022年の今年は57年目。 コロナで過去2年間は大々的なお祝いが出来ず、3年ぶりの祝祭。マリーナベイを背景に設置されたステージを中心に盛大なパレードが行われた。 私たちは、朝早めに起きて、今日は以前から気になっていたシンガポールを縦断するCoast to Coast Walkに挑戦。西側のジュロン・レイク・ガーデンから出発することにし、自宅からまずは電車(MRT)に乗ってチャイニーズガーデン駅へ。実は最寄りの駅はレイクサイドだったことに後で気づく。チャイニーズガーデンから出発するか少し迷ったが、コースを踏襲しようと律儀にレイクガーデンまで2キロほど逆戻り。レイクガーデンについて出発点を探すが起点の標識が見つからない。仕方なくレイクガーデンの入り口を起点とした。 レイクサイドの駅からは歩いて数分の距離にある。再び縦断ウォークをする時が来たら、レイクサイドで降りよう。(備忘録)。 そんなこんなで出発まで少し手こずり、すでに午前7時45分くらい。早めに出発しようという目論見はまんまと打ち砕かれる。相当暑さと闘う道のりになりそう。 UV対策と水分補給は忘れないように、楽しもう!
Category: 旅行
織田信長と安土城
2021年3月15日。マリオット琵琶湖から車で湖畔を北上し西の湖のあたりで東へ向かうと30分ほどで安土に着く。まだ3月の半ばだが晴天で車の中は気温が上がり汗ばむほど。 安土城跡の大手道前には無料の駐車場がある。 安土城の正面玄関、大手道の入り口の大手門で入山料700円を払ってパンフレットをいただく。長篠の合戦で武田勝頼に勝った翌年、1576年から3年かけて築城。信長は天主に移り住むが、その3年後、1582年6月2日、明智光秀の謀反により本能寺の変で自刃。49年の生涯を閉じた。そして6月15日には安土城も焼失、落城。明智光秀軍による放火という説もあるが、真偽のほどは明らかになっていない。 大手門から山腹まで180mほど直線的に伸びる部分の大手道は道幅6mと広く力強い。大手門近くの東西には伝羽柴秀吉邸跡、伝前田利伸邸跡がある。入り口近くに重鎮の屋敷を構え睨みをきかせている。信長が将来天皇を迎えるために作らせたものだという。天主から少し降りた場所にある本丸御殿には、天皇を招き入れるための御幸の間があったとのこと。 一方、当時城を訪れる人々の多くは城下町にほど近い百々橋口から二王門(重要文化財。1571年建立。甲賀より信長が移建)そして三重塔(重要文化財。1454建立。甲賀の長寿寺から信長が移建)と摠見寺(そうけんじ)本堂(現在は本堂跡。仮本堂は大手道沿いの伝徳川家康邸跡にある)を通って信長の居住していた天主へ登ったそうだ。神仏を恐れないことで知られる信長だが、標高199mの安土山全体が寺となっている。 そして天主に登る前に寺の本堂を通らせるというのには、精神的な防御壁の意味もあったのではないかと思わされる。一方で仏足石にみられるように、神社仏閣から石材を集めて城の石垣を築いた。信仰の厚い人びとの憤慨させたことは容易に想像できる。 だが、信長は実は形式にとらわれない真の信仰を求めていたのではないか。確か2020年放送の大河ドラマ「麒麟がくる」ではアフリカから連れてきた奴隷を献上する宣教師に、神の愛と人間の平等について信長が尋ねた場面があった。仏教だけでなくキリスト教の本音と建前さえも鋭く見抜き問いただす信長の鋭敏さと真摯さが窺える。信長は神仏を否定したのではなく、それらを自分たちの利得のために利用しようとする自己中心的な人間の弱さを非難していたのではないか。 天主跡からは安土の町、田畑、そして琵琶湖が望める。今は干拓によって四方が陸地に囲まれているが、信長の時代には琵琶湖の内湖に囲まれ、南方のみが開けていたそうだ。琵琶湖を挟んで比叡山もよく見える。ここから比叡山焼き討ちを命じたのか。その際には瀬田の唐橋を通って比叡山に向かったのかと考える。 ここから琵琶湖を眺め、信長は何を思ったのか。天下布武、武徳によって戦乱の世に終止符をうち、平和な時代をきずく。そんな夢を抱いて走り続け、夢半ばにしてその生涯を終えた信長。49歳。ちょうど今の私と同い年。短い生涯だったがとても濃い時間を過ごしたのだろうな。最期にはどんな思いを抱いたのだろう。